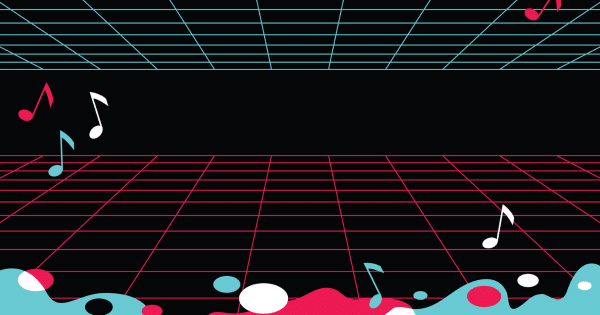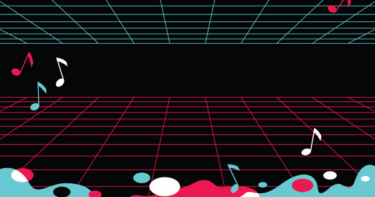「急に再生数が落ちた」「おすすめに全然載らなくなった。これってシャドウバン?」
TikTokを運用していると、一度はそう感じたことがあるのではないでしょうか。
ただし、“なんとなく” シャドウバンだと決めつけてしまうと、誤った対処をして余計に伸びなくなる こともあります。
本記事では、
-
シャドウバンとよくある誤解
-
シャドウバンの主なサイン
-
シャドウバンかどうかを確認する5つのチェック
-
もしシャドウバンの可能性が高い場合の対処法
を、できるだけ「感覚」ではなく「データ」と「手順」で判断できるように整理します。
※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。
-
インサイトで「おすすめ」からの流入を確認する
-
複数本の動画の再生数推移を比較する
-
いいね・コメントのフォロワー/非フォロワー比率を見る
-
ハッシュタグ・検索結果で自分の動画が表示されるかを確かめる
-
テスト投稿と第三者チェックで異常が続くか確認する
これらをすべて行っても、「シャドウバンかどうか」を100%断定することはできません。
しかし、感覚ではなくデータにもとづいて状況を整理することはできます。
TikTokシャドウバンとは?まずは前提を整理する
TikTok公式は「シャドウバン」という言葉を使っていない
まず押さえておきたいのは、TikTokの公式ヘルプや規約に「シャドウバン」という機能名は出てこない という点です。
ユーザー側からは通知も来ないため、「アルゴリズム上の配信制限」が起きていても、明確なラベルは付いていません。
そのため一般的には、次のような状態がまとめて「シャドウバン」と呼ばれています。
-
おすすめ(For You)への露出が極端に減っている
-
フォロワー以外への表示が著しく減っている
-
再生数・いいね・コメントなどの指標が急に落ち込んだまま戻らない
一般的に言われるシャドウバンの状態
多くの解説記事では、シャドウバンを次のように説明しています。
-
コミュニティガイドライン違反などが原因で、
アルゴリズム上、動画の露出が制限されている状態 -
アカウント削除や完全な凍結手前の「警告」「制限」に近い状態
重要なのは、「アカウントの存在自体が消えるわけではない」 ことです。
フォロワーからは普通に見える場合も多く、「外からは分かりにくい制限」がかかっているとイメージすると良いでしょう。
通知が来ないため誤解されやすい
TikTok側から「あなたはシャドウバンされています」といった通知は基本的に届きません。
そのため、
-
単にトレンドが変わっただけ
-
クリエイティブの質が落ちた
-
投稿のタイミングが悪かった
といった要因でも、「全部シャドウバンのせいだ」と感じてしまう ケースが少なくありません。
ここからは、シャドウバンと単なる伸び悩みをどのように見分けるかを整理します。
シャドウバンと「ただ伸びないだけ」の違い
アルゴリズムの自然な波もある
TikTokは、トレンドやユーザーの興味関心の変化が非常に速いプラットフォームです。
同じクオリティの動画でも、
-
トレンドから外れる
-
音源が古くなる
-
似たテーマの動画が増え競合が激化する
といった理由で、再生数が落ちることは珍しくありません。
「直近数本だけがたまたま伸びていないだけ」 というケースも多いので、1〜2本の結果だけで判断するのは危険です。
ガイドライン違反などによる配信制限の可能性
一方で、次のような行為を続けていると、アルゴリズム上の制限(いわゆるシャドウバン)につながる可能性があります。
-
暴力的・差別的・過激な表現
-
著作権を侵害する素材の利用
-
スパム的な連続投稿・ハッシュタグ乱用
-
過度なフォロー・いいねの自動化 など
こうした行為は、TikTokのコミュニティガイドラインや利用規約で禁止・制限されています。
誤認しやすい典型パターン
シャドウバンと誤解されやすいパターンとして、例えば次のようなものがあります。
-
ひとつの「バズ動画」の数値を基準にしてしまい、それ以外がすべて低く見えてしまう
-
投稿内容が大きく変わり、既存フォロワーとの相性が悪くなった
-
ターゲットが狭すぎる(ニッチすぎる)企画に寄せた結果、母数が小さくなった
こうしたケースは、コンテンツの方向性や企画を見直すことで改善できる ことが多く、必ずしもシャドウバンとは限りません。
シャドウバンの主なサイン一覧
ここからは、「シャドウバンの可能性があるときによく出るサイン」を整理します。
この後の5ステップ確認で、これらのサインをまとめてチェックしていきます。
おすすめ(For You)からの流入が極端に減る
シャドウバンが疑われるとき、最も分かりやすいのがおすすめ(For You)からの流入数の減少 です。
-
それまで全体の大半を占めていたおすすめ流入が、急にほぼゼロに近づく
-
フォロワーからの視聴はある程度続いているのに、新規視聴がほとんどない
こうした場合は、露出範囲が強く制限されている可能性があります。
動画の再生数・いいね・コメントが急激に落ち込む
-
直近の複数投稿すべてで、再生数がそれまでの平均値から大きく下回っている
-
いいね・コメント・シェアなどのエンゲージメントも一緒に落ちている
といったパターンも、配信制限を疑うサインになります。
ただし、「たまたま企画が外れた」「クリエイティブの質が落ちた」可能性もあるため、他のサインと合わせて判断することが重要です。
ハッシュタグページや検索結果に表示されにくくなる
-
投稿で使用したハッシュタグを検索しても、自分の動画が「最新」タブにほとんど出てこない
-
検索キーワードで探しても、自分の動画が極端に見つかりにくい
といった現象も、多くの解説でシャドウバンの兆候として挙げられています。
エンゲージメントが既存フォロワーに偏る
-
いいね・コメントをしているユーザーの多くが既存フォロワー
-
「フォロワー以外からの反応」がほぼゼロに近い状態が続く
この場合、新規ユーザーへの露出が大きく絞られている 可能性があります。
シャドウバンかどうかを確認する5つのチェック
ここからは、実際にシャドウバンかどうかを確認するための5ステップを紹介します。
上から順番に実施していくことで、ある程度ロジカルに判断できるようになります。
ステップ1:インサイトで「おすすめ」流入を確認する
まずは、アカウントのインサイト(アナリティクス)から、
-
直近7〜28日の「おすすめ(For You)」からの再生数
-
その前の同じ期間の「おすすめ」からの再生数
を比較します。
ポイント
-
単発の動画ではなく、「期間全体の傾向」を見る
-
アカウント規模ごとに見え方が違うため、「自分の平常値」と比べることが重要
もし、
-
以前は多くの再生がおすすめ経由だったのに、
-
最近はほぼフォロワー経由だけになっている
といった状態であれば、配信制限の可能性が高まります。
ステップ2:動画の再生数推移をチェックする
次に、直近10〜20本程度の動画の再生数推移 を一覧で眺めてみてください。
-
全体的に右肩下がりになっているか
-
特定の動画だけが極端に低いのか
ここで大きく分かれるのは、次の2パターンです。
-
ほぼすべての動画で、一斉に再生数が落ちている
→ アルゴリズム上の評価低下や配信制限の可能性が高い -
特定のテーマ・企画だけが落ちている
→ コンテンツ側の課題やトレンド変化の可能性が高い
後者の場合は、まず企画や方向性の見直しを優先したほうが良いケースが多いです。
ステップ3:いいね・コメントの内訳(フォロワー/非フォロワー)を見る
インサイトで、いいね・コメントをしているユーザーの傾向も確認します。
-
以前は「フォロワー以外」からの反応も一定数あったのに、
-
最近はほとんどが既存フォロワーだけになっている
という状態が続いている場合、新規ユーザーへの露出が大きく制限されている可能性があります。
ステップ4:ハッシュタグ・検索結果で自分の動画を探す
投稿時に使用したハッシュタグや、動画のキーワードで実際に検索してみましょう。
-
TikTokの検索バーにハッシュタグやキーワードを入力
-
「最新」タブを開き、自分の動画が表示されるか確認
-
同じタイミングで投稿した他ユーザーの動画との比較も行う
自分だけ極端に表示されていない場合 は、やはり配信制限の可能性が高まります。
ステップ5:テスト投稿と第三者チェックを行う
最後に、テストとして新しい動画を1〜2本投稿し、以下を確認 します。
-
投稿後数時間〜1日で、いつもと違う異常な動きが出ていないか
-
フォロワーや知人に「フィードに出てきているか」を確認してもらう
もし、
-
テスト投稿も含め、ほぼすべての動画が「ごく一部のフォロワーにしか届いていない」
-
規約違反を疑うような要素がないのに、異常な低パフォーマンスが続く
という場合は、シャドウバン状態の可能性がかなり高いと判断できます。
シャドウバンの原因になりやすいNG行為
確認の結果、シャドウバンの可能性が高い場合は、原因を一つずつ潰していく必要があります。
代表的なNG行為を整理します。
コミュニティガイドライン違反コンテンツ
-
暴力的・差別的・過度に過激な表現
-
嫌がらせ・いじめにつながる表現
-
性的な表現や年齢制限が必要な内容
-
健康被害を招くおそれのある誤情報 など
このような内容は、ガイドライン違反として削除や制限の対象になり得ます。
過度なハッシュタグ乱用・ミスマッチなタグ付け
-
トレンドに乗ろうとして、関係のない人気ハッシュタグを大量に付ける
-
コンテンツと明らかに無関係なタグを付けてしまう
といった行為も、スパムとみなされるリスクがあります。
フォロワー・いいねの不自然な増やし方
-
フォロワー購入サービスの利用
-
ボットによる自動いいね・自動フォロー
-
相互フォロー・相互いいねを強制する企画
などは、プラットフォーム側に不自然な挙動として検知される可能性が高く、長期的に見るとアカウント評価の低下につながります。
シャドウバンだった場合の対処法と復活戦略
まず見直すべき投稿・設定
シャドウバンの可能性が高いと判断したら、次の順番で見直します。
-
ガイドライン違反の可能性がある動画を非公開・削除する
-
タイトル・説明文・ハッシュタグの表現を見直す
-
プロフィールや外部リンクに問題がないか確認する
原因となり得る要素を減らし、クリーンな状態に戻すことが第一歩 です。
投稿頻度を一時的に落として様子を見る
-
3日〜1週間程度、投稿頻度を落とす
-
その間に、過去投稿のインサイトを分析し、今後の企画を練る
といった「小休止」を推奨する解説も多く見られます。
ただし、完全にゼロにしてしまうのではなく、「問題のない良質な投稿」を少量続ける方が良いケースもあります。
ガイドラインを意識した新しい動画の作り方
シャドウバンからの復活を目指すうえで重要なのは、
-
視聴者にとって価値があるコンテンツ(役立つ・楽しめる)
-
ガイドラインに抵触しない安全な表現
-
最後まで見たくなる構成(フック・オチ・ストーリー)
といった 基本に立ち返った動画制作 です。
問い合わせ(ヘルプセンター)を検討するタイミング
-
自分なりに原因を洗い出して改善したにもかかわらず、
-
長期間(数週間〜)異常な状態が続く場合
には、TikTokのヘルプセンターから状況をフィードバックすることも選択肢です。
シャドウバン専用の窓口があるわけではありませんが、状況を具体的に伝えることで、何らかの対応が行われるケースもあります。
アカウントを作り直すべきか判断するポイント
-
まだフォロワーが少ない初期段階
-
ガイドライン違反の履歴が多く、立て直しが難しい
-
長期間にわたり改善の兆しが見られない
といった場合には、新規アカウントを検討することもあります。
ただし、同じ端末・同じIPで同じような運用をすると、再び同じ状態になるリスク も指摘されています。
企業・店舗アカウントが押さえるべき運用ルール
企業・店舗アカウントの場合、シャドウバンは「再生数が落ちる」という問題にとどまらず、
-
キャンペーン成果の悪化
-
ブランドイメージの低下
-
社内での説明責任
など、影響範囲が広がりがちです。
ブランド毀損・炎上・凍結リスクを避けるガイドライン
-
政治・宗教・差別的なテーマを扱わない
-
利用規約・法律に反するおそれのある表現を避ける
-
タレントや第三者の権利(肖像権・著作権)に配慮する
といった 社内ガイドラインを作成し、運用担当者間で共有 しておくことが重要です。
数字が落ちたときの社内説明の基本ロジック
数字が落ちたときは、次のようなフレームで社内報告すると、感情論になりにくくなります。
-
現状:いつから、どの指標が、どの程度落ちているか
-
原因仮説:
-
トレンド要因
-
コンテンツ要因
-
プラットフォーム側の制限要因
-
-
対応策:
-
直近の改善施策(コンテンツ・投稿設計の見直し)
-
中長期的な運用ルールの整備
-
このように、「シャドウバンかどうか」ではなく「どう改善するか」にフォーカスを移す ことが大切です。